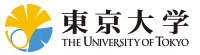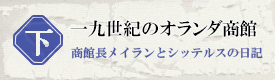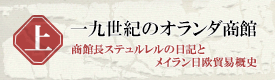外交の世界史の再構築
2025年度 活動報告
2025年8月10日~11日、東京大学史料編纂所で第15回研究会を開催しました。
コメンテータの方に事前に原稿を読んでいただき、当日コメントを頂戴した後、全員で討論をしました。
8月10日
<司会:原田亜希子>
・飯田洋介(菊池雄太論文コメント)
・酒井雅代(辻大和論文コメント)
・諫早庸一、後藤春美(総論コメント)
・黛秋津(森永貴子論文コメント)
・松本英実(堀井優論文コメント)
・参加者
飯田洋介、諫早庸一、江口絵理、岡本隆司、川口洋史、菊池雄太、木土博成、木村可奈子、後藤春美、酒井雅代、塩谷哲史、大東敬典、辻大和、原田亜希子、堀井優、松井真子、松方冬子、松本あづさ、黛秋津、皆川卓、森永貴子
8月11日
<司会:皆川卓>
・宇山智彦(塩谷哲史論文コメント)
・渡辺美季(木土博成論文コメント)
・総合討論
・今後の予定
・参加者
飯田洋介、諫早庸一、宇山智彦、江口絵理、岡本隆司、川口洋史、木土博成、木村可奈子、酒井雅代、塩谷哲史、大東敬典、辻大和、原田亜希子、堀井優、松井真子、松方冬子、松本あづさ、皆川卓、森丈夫、森永貴子、渡辺美季

2025年8月9日、東京大学伊藤国際学術研究センター3階特別会議室において国際研究集会「一国史を作る ―ウズベキスタンと日本―」を開催しました。対面参加者25名(事前申込23名)、オンライン参加者20名(事前申込46名)、合わせて45名の参加者により、有益な議論が行われました。
日時:2025年8月9日(土)15:00-18:00
場所:東京大学 伊藤国際学術研究センター3階 特別会議室(定員30名)オンライン同時配信
使用言語:英語・日本語
Uzbekistan is now trying to build its own history, just as Japan once did. In both countries, diplomatic history and the translation of foreign documents related to their countries have played a major role in this process.
There are many similarities in the historical narratives about the Khanate of Khiva (1512-1920) and Tokugawa Japan (1603-1868). Vasilii Barthold (1869-1930) stated that Khiva is isolated, and many researchers followed suit. In a similar way, western observers have used the term "Sakoku" (closed country/national isolation) to describe Tokugawa Japan, and much research has been conducted within the scope of that thesis.
In this workshop, we would like to discuss how to talk about our national and world history, and who “we” are when we talk about history.
ウズベキスタンは今、日本がかつてそうしたたように、自国史を築こうとしている。その過程で外交史研究や、自国に関連する外国文書の翻訳が、どちらの国でも大きな役割を果たしてきた。
現在のウズベキスタンに存在したヒヴァ・ハン国(1512-1920年)と徳川日本(1603-1868年)についての、歴史の語りには共通点が多い。
ロシア・ソ連の中央ユーラシア史家ヴァシリイ・バルトルド(1869-1930)が、ヒヴァは孤立していたと述べ、多くの研究者がそれに倣った。
一方、西洋の観察者たちは徳川日本を「鎖国」という言葉で表現し、その結論の範囲内で多くの研究が行われてきた。
本ワークショップでは、ウズベキスタンで国民史構築を担っている第一線の研究者を招き、私たちの国の歴史と世界史をどのように語ればよいのか、そして歴史を語る際の「私たち」とは何者なのかについて、議論したい。
<プログラム>
司会:塩谷哲史(筑波大学人文社会系教授)
趣旨説明:松方冬子(東京大学史料編纂所教授)
講演:ウズベキスタンにおける国民史構築の過程と外交史研究の動向
アッラエヴァ・ニゴラ(ウズベキスタン共和国科学アカデミー アブー・ライハーン・ビールーニー名称東洋学研究所教授)
話題提供:「鎖国」と「封建制」―世界史のなかの日本の自画像―
松方冬子(東京大学史料編纂所教授)
総合討論
主催:外交史プロジェクト(三菱財団人文科学研究助成「外交の世界史の再構築」)
共催:JSPS科研費24K00121、東京大学史料編纂所共同利用共同研究拠点特定共同研究海外史料領域「本所所蔵在外日本関係史料の多角的利用のための翻訳研究」、東京大学史料編纂所
後援:日本学士院



(参加記)
2025年8月9日(土)に開かれた国際研究集会「一国史を作る ―ウズベキスタンと日本―」に参加した。ウズベキスタン共和国科学アカデミー・ビールーニー東洋学研究所のアッラエヴァ・ニゴラ教授により、「講演:ウズベキスタンにおける国民史構築の過程と外交史研究の動向」の題目で講演が行われ、ウズベキスタン史に関する帝政ロシア、旧ソビエト連邦、独立後のそれぞれの研究史の動向について整理されたのち、ヒヴァ・ハン国の外交史料を用いた最新の研究について紹介された。次に史料編纂所の松方冬子教授より「鎖国と封建制―世界史のなかの日本の自画像―」として近世日本の対外関係や封建制に関する話題提供が行われた。
ニゴラ教授には、松方教授の代表科研で2023年9月にタシュケントを訪れた際にお目にかかって以来である。その際にニゴラ教授から伺ったヒヴァ・ハン国の外交史研究に関する話が興味深かった記憶があるが、今回はさらに別の史料、切り口で報告され、理解が深まった。教授はロシアの東洋学者バルトリドがヒヴァ・ハン国が孤立している、とかつて評価したものの、近年のマルチアーカイヴァルな外交史料研究によってヒヴァ・ハン国がロシアだけでなくイランやオスマン帝国、ブハラ・ハン国等と多様な関係を結び、決して孤立していなかったことを外交史料にもとづいて説明された。
質疑応答では西洋の観察者が日本が「鎖国」している、と評価したことと、ヒヴァ・ハン国の「孤立」認識の類似性に話が及んだが、同様なことはほかの近世アジアの諸国家についてもいえるかもしれない。私が専門とする近世朝鮮は、日本や清中国との間に国交があり、貿易が行われていたものの、19世紀には「隠者の国」(Hermit Nation)と欧米人にみなされていた。比較史的な観点の重要性を今回の研究集会で強く認識することとなった。
2025年6月7日、東京大学伊藤国際学術研究センター3階特別会議室において国際研究集会「外交の世界史の再構築」を開催しました。対面、オンライン、合わせて67名(事前登録127名)の参加者により、活発な議論が交わされました。
日時: 2025年6月7日(土)10:00~15:00
会場:東京大学伊藤国際学術研究センター3階 特別会議室(オンライン同時配信)
使用言語:英語
Program
This workshop discusses legal aspects of global diplomatic history from the sixteenth to the nineteenth century and challenges narratives of diplomacy frequently dominated by Eurocentric perspectives.
Redefining three terms that have informed such narratives, “consuls” as heads of foreign residents, “tariff” as taxation on transportation, and “treaties” as inter-state agreements, our research project “Global History of Inter-State Relations” seeks to identify legal commonalities, rather than segmentation, that shaped inter-state relations around the world during that period. In this workshop, we invite two researchers from the United States who have worked together with the same research agenda, but using different concepts, namely “protocol”, “jurisdiction”, and “protection”. The workshop explores the still untapped, legal dimension of global connections through the records of the Dutch East India Company and British India.
本研究集会は、16~19世紀のグローバル・ヒストリーにおける外交と法の問題を議論する。
主催者外交史PJは、《領事》《関税》《条約》に着目しつつ、世界各地における外交のあり方に共通点を見出そうとしている。
本研究者集会では、同じように、protocol, jurisdiction, protection という概念を用いて、世界の各地における政体間の関係性の共通点を見出そうとして、共同で執筆活動を重ねてきたアメリカの研究者2名を招き、オランダ東インド会社の外交と、英領インドの支配を実例に、この問題を考える。
Chaired by Travis Seifman (Art Research Center, Ritsumeikan University)
Introduction:Fuyuko Matsukata (Historiographical Institute, The University of Tokyo)
"Categorizing VOC's East Indian Treaties"
Norifumi Daito (Historiographical Institute, The University of Tokyo)
"The Company’s Small Wars: Dutch Violence and Trade in Seventeenth-Century East and Southeast Asia"
Adam Clulow (The College of Liberal Arts, The University of Texas at Austin)
Lauren Benton (Department of History, Yale University)
"Diplomacy and Colonial Rule in British India"
Haruki Inagaki (Department of History, Aoyama Gakuin University)
Comments:Yasunori Kasai (Department of Greek and Latin Classics, The University of Tokyo)
General Discussion
主催:外交史PJ(三菱財団人文科学研究助成「外交の世界史の再構築」)
共催:東京大学史料編纂所共同利用共同研究拠点特定共同研究海外史料領域「本所所蔵在外日本関係史料の多角的利用のための翻訳研究」、東京大学史料編纂所


(参加記)国際研究集会を終えて
今回の国際研究集会は、大成功だったと思う。換言すれば、現時点では、これ以上のものは望めないだろう。
当初考えていた「同じ方向性」は確認されたし、今まで考えていたことは間違いないと思えた。
議論の中で、頭に浮かんだけれども、言葉にできなかったこと(終了後の会場で個人的に話したこと)として、以下の2点がある。
1点目は、外交の世界史PJに「戦争」「violence(本研究集会で、『武威』という訳語も提案された)」が視野に入っていない理由として、戦後日本の「ほっとけ平和主義」があるということである。私の考えに、知らず知らずのうちに影響を与えているようである。これを、”Let-It-Be Policy”または“Keep-Them-Going Policy”と訳してみたが、とりあえず日本事情に通じた人にならわかってもらえたらしいことは収穫だった。
2点目は、軍事権力/経済権力/宗教・学術権力が与えられるものとして、当初Protection/Enrichment/Healingを考えていたが、Protection/Eating and Drinking/Recognitionのほうが良いかもしれない、という話になった。大切なことは、これらが「概念として(言語を通じて)」理解できるものではなく、言語以前に、体感的にわかるものだろうということである。おそらく、3歳の幼児でも、1歳の乳児でさえ、この3つは理解できるのではないだろうか。こう考えれば、将来的には、発達心理学、児童心理学といった分野とも対話が可能なのではないだろうか。
それにつけても、英語発信のサポートは喫緊の課題だと思えた。正直に言えば、喉から手が出るほどほしい。私の貧弱な語彙でも、言いたいことの一端は言えるのだが、「書く」となるとハードルはさらに上がる。個人の努力や友情に頼らなくてもどうにかなる方法はないのだろうか。
救いは、今回も、国内外の多くの友人たちが集ってくれ、意見を交換し、楽しいと言ってくれたことである。
別れるとき、ローレン・ベントン氏から「We should keep in touch. 一緒に、私たちと同じ考えの人たちを増やしましょう。」と声をかけられた。私の気力がどこまでもつかわからないけれども、こんなとき、やはり“Global community” というものが、たしかに存在するという気がしてくる。そして、離れていてもわかり合えることを、人間の違いよりは共通性を、分断ではなく連帯を、どうしても信じたくなってしまうのである。
(参加記)
On Saturday June 7th, I had the pleasure of attending the workshop on the Global History of Inter-State Relations at Itō Center, University of Tokyo. The event, organized by Professor Matsukata Fuyuko, brought together specialists from inside and outside Japan to discuss recent scholarship on the records, features, and logic of encounter in the early modern world, as well as reflections and recent trends in the relevant historiography. In her introductory remarks, Professor Matsukata laid the groundwork for discussion by highlighting the respective points of emphases of her research into Eurasian diplomacy and a series of papers co-authored by Professors Laura Benton (present in Tokyo) and Adam Clulow (participating remotely from the United States). Matsukata noted that these complementary strands of research disaggregated assumed categories of encounter, dispensing with binary models in favor of broader pan-Eurasian comparison. For example, Matsukata's work emphasizes "straddler" communities, often merchants, who moved among polities, negotiated economic and political privileges, and negotiated much of what is thought of as inter-state or inter-polity diplomacy at this time. In contrast, but not in conflict, Benton and Clulow's articles have explored the legal frameworks that structured core aspects of inter-polity relations, among them claims to jurisdiction and the requests and offering of protection. These comments helped contextualize the presentations that followed.
Daito Norifumi presented on the types of agreements entered into by the Dutch East India Company in the seventeenth century. His work was both historical and historiographical, as he classified the various agreements entered into at the time and analyzed how various "contracts" were or were not included in subsequent compendia of primary sources that have shaped the study of the VOC, the treaties it signed, and the entities it negotiated with. For example, the Corpus Diplomaticum, an important twentieth-century compendium of primary sources, includes no treaties agreed by the VOC or Dutch in Europe. Nor does it include "private" contracts. In contrast, the "contract books" providing much of the material for the Corpus, includes what are best described as private contracts, but contains no agreements entered into by the VOC with Japan, despite the centrality of the Japanese factory to VOC operations at the time (the Corpus included such examples, drawing from other materials). Professor Daito also provided an example of a contract signed between the VOC and Japanese traders in Cambodia as an example of agreements that challenge common categorization. Daito's analysis facilitated comparisons between Matsukata's work and that of Clulow and Benton, by looking at the types of agreements each body of scholarship has investigated to this point, including the power relations of each party and the nature of the contract as private or political.
Laura Benton and Adam Clulow presented an in-progress article on the importance of perpetual "small wars" to the advancement and contestation of VOC claims across East and Southeast Asia. These conflicts have gone unstudied by most scholars, but by focusing on them the two scholars show that the VOC was involved in some form of conflict almost every year. Moreover, this violence was not simply an imposition of Western power into non-Western space. Instead, these conflicts — often taking the form of raids for goods and captives — fit within established patterns of violence, diffusion, and negotiation. Such small wars were foundational to company activities and a key feature of inter-polity relations not properly appreciated in more common narratives of grand state conflict. Laura Benton also provided an overview of her recent monograph on Empire (They Called it Peace - 2024) which argues for the centrality of perpetual small wars in the regime of violence that defined European overseas empires. This study fits into her work with Adam Clulow on the protection and jurisdiction as key concepts for understanding the legal frameworks that governed trade, violence, and inter-polity relations in the early modern world.
Professor Haruki Inagaki's presentation took two concepts central to Benton and Clulow's work — protection and jurisdiction — and applied them to the activities and negotiations of the British East India Company in India. Departing from the existing tendency to examine EIC activities as colonial history, Inagaki instead looked at relations in terms of diplomatic history. In the treaties negotiated and tested among a plurality of authorities on the subcontinent, he found examples of the same jurisdictional politics that Benton and Clulow argue to be foundational to the legal frameworks structuring inter-polity relations. Inagaki also found these dynamics spurred the amorphous boundaries of law, violence, and justice emerging between the EIC and Indian princes retaining measures of internal autonomy even as they ceded jurisdiction on many "external" matters. Professor Inagaki concluded by suggesting that the ambiguities inherent to these treaties laid the foundation for the "diplomatic violence" discussed in Benton and Clulow's work.
Professor Kasai Yasunori closed the formal proceedings by offering comments on the panel presentations, drawing on his knowledge of classical legal history and traditions. He noted the long-rooted mistrust of strangers and raiders as actors moving across boundaries, citing the Odyssey as one example. He responded to Benton and Clulow's paper by tracing the history of jurisdiction (literally, "speaking the law") within classical and medieval traditions, as well as offering examples of how contracts and penalties were enforced when partners failed to uphold contracts. Professor Kasai also highlighted the importance of reciprocity as a concept in many of these negotiations, a theme that resonated with much of the recent work by Benton, Clulow, and Matsukata.
A Q&A session following the formal presentations allowed for clarification on concrete questions as well as reflections on broader themes. The most notable of these (for me) were questions related to violence, such as its "legibility" across cultures, its role in the establishment of legal cultures across societies, and its roles within the scholarship of those gathered, including my own.
In sum, the workshop offered a welcome opportunity to discuss the work and research trajectories of multiple scholars together with those scholars themselves. It was also an important opportunity to speak across subfields and traditions of academic training, a strength of many of the events organized by Professor Matsukata and her peers at Todai and beyond. It was a pleasure to attend, and it provided me with much to think about with regards to advancing my own work and assessing and engaging with the work of others scholars across fields.
(参加記)
ワークショップ「外交の世界史の再構築」は、様々な点で本研究会にとって、ひいては日本における「外交の世界史」という分野にとっても、有益な機会となったと思う。何より貴重だったのは、メインゲストであるローレン・ベントン氏が自らの外交に関する立場を明確に提示し、それが、冒頭で松方冬子氏が提示した本研究会の立場と共鳴するものであったことである。ベントン氏は、主権国家のみを主体としたヨーロッパ国際法システムの拡大として捉える外交史観を批判し、複数の国際システムの存在の下、共通性を模索しながら、諸主体が外交を行う歴史像を検討すべきであると論じた。これは朝貢システムという視点のみから前近代東アジア外交史を解釈する従来の見解を批判的に捉える、本研究会の立場と共通しよう。ベントン氏は、多元的な法域という方法視角を用いて新たなグローバルヒストリー研究を開拓しつつあるが、本研究会がこうした新しい世界的な潮流と接続していることがわかり、研究の足場が一層固まったように思える。
諸外国出身の研究者を含めて多様な参加者があり、通常の本研究会ではあまり出ないような意見・質問が多く出た点は、ワークショップを開く最大の面目躍如であった。そこでも進出勢力の利益追求の問題に関する質問やアレクサンドロビッチの国際法のグローバルヒストリーに関する意見に応答する中で、上記のようなベントン氏の思想がより鮮明な像を結んでいったのが印象的であった。
アメリカ大陸を研究のフィールドとする筆者にとっては、ベントン氏がスペインのレコンキスタを例に挙げながら、従来は征服活動として捉えられていた事象を、広く外交という視点から解釈できるという指摘も興味深かった。レコンキスタでは、キリスト教勢力は、攻撃相手と降伏条約のプロトコルを交わすことで、一時的な休戦状態を作り出し、秩序の構築を模索したという。ナスル朝のように、その結果、イスラーム勢力が臣下vassalとしてキリスト教徒勢力の保護下に入ることも「外交」のバリエーションとして理解される。アメリカ大陸においても、ヨーロッパ勢力による征服に焦点が当てられた従来の見解に代わって、ヨーロッパ人が先住民と条約を交わしながら進出していった点が近年強調されているが、ベントン氏の意見から、アメリカ大陸の状況はヨーロッパでの経験と規範に端を発するのではないかと考えさせられた。またこうした「保護下に入る」という関係は、ワークショップ冒頭で松方氏が提示した外交を考えるキーワードの一つ「保護」の規定に見られる、「支配者間の法的権限の共有」にも通じるのではないだろうか。文化、規範、軍事力が異なる諸主体が出会う前近代の空間においては、支配下に入り、保護を得ることは、外交関係のパターンとしてもっと重視されるべきなのだと思われる。
大東敬典氏と稲垣春樹氏の報告は、本研究会で従来取り組んできた、こうしたレベルの異なる諸主体の織り成す外交を実証的に提示するもので、「外交世界史の再構築」の具体的な手触りを生き生きと感じさせた。他方で、ベントン氏とアダム・クルロウ氏の報告 “The Company’s Small Wars”が新鮮だったのは、本研究会ではあまり取り上げてこなかった「戦争」の問題を取り上げた点であった。ベントン氏とクルロウ氏は、近世のグローバルな空間で帝国的進出を考えるためには、戦争を考えることは不可欠だと提唱する。しかしながら、両氏が重視するのは、帝国拡大のための暴力や利益追求目的としての戦争ではなく、通商交渉や外交と一体化した手段として戦争があったことである。報告でも、オランダ東インド会社のようなヨーロッパ勢力は、襲撃raidや捕虜収奪captive takingといった小さな戦争small warsを通商交渉の材料として用いていた諸事例が提示された。この視点が本研究会にとって重要なのは、本研究会では、通商や保護をめぐる交渉や恒常的外交は数多く取り扱ってきたが、必ずしもそれがどのように成立してきたかを検討してきたわけではないためである。「通商」が「戦争」と深く絡み合っているとすれば、本研究会が扱うべき対象は、講和条約や休戦条約などにも広がることになろう。他方、こうしたヨーロッパ勢力による暴力がどのように法の多元主義という従来のベントン氏の理論と接合するのかについても、もう少し聞いてみたいように思った。
ともあれ、学界のワークショップの多くが科研の報告会や個別研究の寄せ集めになってしまいがちな中、地域・時代を異にする多くの研究者がテーマとスタンスを共有しつつ、長時間の議論の場を作ったことは、極めて異例ではないだろうか。このような場に参加できたことは極めて幸運であった。
(参加記)
3報告とも具体的な事例を通し、「現場」から見えてくる新たな像や問題提起をご提示いただいた。特に印象的だったのは、戦争とは呼ばれない小規模の暴力(”small wars”、まだ不完全で暫定的に用いているということであった)の重要性に着目したLauren Benton氏が、この報告を行う契機として、歴史学では暴力を不思議なことのように捉えている、という主旨の発言をされていたことであった。筆者はよく起きるありきたりなことという認識であったのだが、ありきたりに捉えるからこそ、それ以上深く考えていない部分があったように思う。改めて自分のフィールドにおける“small wars”について考えてみたい。
(本ページの無断転載を禁止します。)