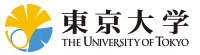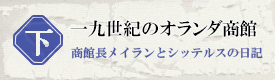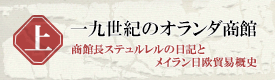長崎口の形成
鹿島学術振興財団研究助成 2019年度
長崎口の形成―15~19世紀の長崎から見た日本列島の国民国家形成と対外関係
The Formation of the Nagasaki-Gate: Japan’s State-formation and Foreign Relations from the Viewpoint of Nagasaki in the 15-19 Centuries
本研究の趣旨
近世日本は「鎖国」というイメージが強いが、実際には、「国書」による外交(対朝鮮)、支配―従属(対琉球)、「国書」を伴わない貿易(対清、オランダ)、国家が形成されてない土地への植民(対蝦夷地)と、多様な対外関係を形成していた。一方、中世から近世を経て近代にいたる外交・対外関係の変容は、列島における(国民)国家形成と連動していたはずである。従来はヨーロッパを基準として、日本がそれと違う(「鎖国」)と説明するか、むしろ中国と似ている(「海禁・日本型華夷秩序」)と説明してきた。しかし、本研究は、ヨーロッパや中国を基準とすることにも、「日本」を主語とすることにも疑問を呈しつつ、新しい世界史のなかで近世日本の歴史像の構築を目指す。
考察の対象は、中世までそれぞれ独自の経済・文化圏をなしていた列島と大陸をつなぐ4つの交易路(海の道)が、近世に「四つの口」、すなわち、対馬口(対朝鮮)、長崎口(対中国、東南アジア、オランダ)、薩摩口(対琉球)、松前口(対蝦夷地)に収斂していったと考え、「四つの口」が蒸気船の導入その他の理由で近代には意味を失うまでである。国内史的にみると、古代以来の律令制的な諸制度が残るなか、軍事的な徳川政権が誕生し、さらにそのもとで利益共同体としてのnationが藩レベルで生まれ、戊辰戦争で統合されるという仮説が考えられる。本研究では、とくに長崎に住む人たちが、北九州から五島列島をへて浙江を結ぶ海の道を独占した、という観点から長崎口の形成を見直すことを出発点に問題に取り組む。
具体的な方法として、日本史だけでなく、「四つの口」の向こう側にあったロシア、現在の中国東北部(女真・満洲族)、朝鮮、明・清、琉球の専門家が集まることで、分野を超えた語りを可能とする言葉の構築を進めながら研究を行う。今まで近世日本史を語るためにのみ使われてきた「四つの口」論、権力=空間論などを、世界のほかの地域にも当てはめて考えてみる。上記に示したような4つの海の道が特定の都市や藩に独占されるという見取り図は、より一般化するならば、地理的にある程度決定される交易路が、そこで活動する商人たちが互いに競争する中、権力との関係で、どのように独占されたのか、という問題であり、世界史的にも汎用性が高い議論ではないかと思われる。
メンバー
研究代表者
松方 冬子
共同研究者
橋本 雄、織田 毅、村尾 進、吉村 雅美、海原 亮、荒木 和憲、黒嶋 敏、谷本 晃久、平岡隆二、岡本 隆司、杉山 清彦
活動報告
2020年1月29日~31日、海原亮、木土博成、木村可奈子、大東敬典、松方冬子が鹿児島に出張し、研究会(報告タイトル「朝鮮通信使と琉球使節」)を行いました。
巡検参加記
2020年1月29~31日、鹿児島巡検を行った。29日は鹿児島県歴史資料センター黎明館を訪れ、30日は鹿児島市から足を伸ばして、指宿市考古博物館時遊館COCCOはしむれ、山川港、南さつま市坊津歴史資料センター輝津館、31日は日置市沈壽官窯、最後に尚古集成館を訪問した。
初日、黎明館の会議室において、京都大学の木土博成さんから18世紀初めの薩摩藩をめぐる国内外の状況ついてのご報告があった。また翌日からは住友史料館の海原亮さんが車でご案内くださり、「四つの口」形成に関する史跡を数多く見て回ることができた。
三日間の巡検では多くのことを学んだが、中でも興味深かったのは、鹿児島から山川港を経て坊津へ向かう間の海の変化である。朝、鹿児島市を南に向かう車内から見る海は穏やかで、正午過ぎに着いた山川も心地良かった。しかし鹿児島湾を離れると、迫力のある外洋が姿を現し、少し雨が降ったこともあって、坊津に入ると荒波が響いていた。海風が吹きつける輝津館から入江を眺めると、当時の来航船が入港時に経験したであろう相当な苦労が思いやられ、先の山川の静けさが一層引き立つように思われた。ところが、同館の橋口亘さんによると、そうとも言えないそうである。薩摩藩が山川を玄関口と定めた時、渡来は随分容易になったでしょうと伺うと、船が黒潮によって東へ押し流されてしまう危険性があるため、西端に位置する坊津を目指す方が実は理に適っているのだという。そこで改めて、琉球から黒潮を渡り鹿児島湾に向かう航海の難しさを想像すると、坊津と山川が実際の距離以上に離れた場所であるように思えてきた。その一方、中国南部や東南アジア大陸部から黒潮の北側を進む船には、坊津は恰好の目的地だったのだろう。そしてそれは、同様の航海で辿り着ける九州西岸の全ての港について言えるのかもしれない。そう考えると、俄かに平戸や長崎が身近に感じられた。一体南シナ海や東シナ海を渡り来る船に九州西岸一帯はどのように映っていたのだろうか。
坊津の特徴について、地域には坊、泊、久志、秋目という四つの入江があり、一般に坊津と呼ばれているのは坊である。坊の入江は湾曲しているため、外洋の大波が奥まで入り込まず、船舶の停泊に適するが、他の入江は外に開いていて波をまともに受けてしまう、というお話も伺った。この坊津成立に関する「四つの浦」論は、「四つの口」形成について、国家の他にも様々な側面を考慮する必要性を伝えるだけでなく、そうした総合的手法によって、東アジア以外の海港との比較研究の可能性も示しているように思われる。
第一に、海港の存亡と国家の緊密な関係は近世東アジアに限らないのではないだろうか。18世紀のペルシア湾では、多くの港がインド洋交易の利益をめぐって激しく競合した。その内有力なのは、ブーシェフル、バスラ、マスカトであったが、それぞれザンド朝、マムルーク政権、ブー・サイード朝という新興勢力の拠点港であった。東アジアの国家と比較すると領域が小さく、等しく「国家」と呼ぶのは不適切かもしれないが、ブー・サイード家の長は現在もオマーン国の君主であり、マスカトは同国の首都である。継続性という点でも注目に値すると思う。
政治権力以外の側面についてもマスカトを例にとると、マスカトは、ペルシア湾の入口に位置し、インド洋交通の要衝として機能した点や、岩山に囲まれた天然の良港である点で、坊津とよく似ており、海港の成立における海洋からの連絡の重要性を伝える。その一方、マスカトは内陸部との連絡が難しく、そのためブー・サイード朝の君主はマトラフという近郊の港も活用した。このマスカトとマトラフの関係は、坊津と山川の関係と相通じるものがあるかもしれない。前述の黒潮の問題も併せて考えると、坊津と山川が異なる機能を持った二つの「口」に見えてくるようである。またマスカトは、ペルシア湾にあっては、来航者に良質な飲み水を供給できる貴重な港であったと言われている。これについてはケンペルが自身の体験に基づいて記録しているが、日本の「口」については何か書き残していないだろうか。18世紀、ペルシア湾ではアラブ住民による海運・交易が非常に活発化し、彼らの活動はペルシア湾から紅海方面、さらにアラビア海を超えてインドや東南アジア方面にも及んだ。マスカトの発展は彼らのネットワークによって支えられていたが、坊津や山川と地域の事業者との関係はどのようなものだったのだろうか。地域商人のネットワークから「口」の形成や国際秩序について考えてみることにも意味があるだろう。
こうして「薩摩口」から離れてみると、近世東アジアの国際関係という枠組みの他に、例えば港市論や商人論のような、特定の空間・時間設定からやや自由な観点から「四つの口」について考えてみることも有効であるように思われた。そしてその時には、地域にあって歴史と向き合ってこられた方々の知見が大きな推進力となると、私は思う。今回の訪問先でも多くのことを勉強させていただき、そのことを強く感じた。記して感謝申し上げます。

(山川港)

(坊津:画面右側が外洋)
2019年9月28日、東京大学山上会館において、研究会を行いました。木村可奈子、塩谷哲史、辻大和、立石了、堀井優、彭浩、松本あづさ、吉岡誠也、松方冬子が参加しました。今後の研究計画を話し合うとともに、下記の2本の書評報告と討論を行いました。
松本あづさ「『国書がむすぶ外交』へのコメント」
松方冬子「『商業と異文化接触』へのコメント:塩谷、堀井、菊池論文を中心に」
2019年6月28日~30日、長崎において研究会を行いました。以下、3本の参加記と研究代表者からのまとめを以てご報告といたします。
28日 読書会参加記
長崎歴史文化博物館の講座室において、山下範久編『教養としての世界史の学び方』(東洋経済新報社、2019)の読書会を行いました。参加者(敬称略)は、木村可奈子、ジョシュア・バッツ、杉山清彦、関周一、奈良勝司、橋本雄、平岡隆二、松方冬子、森永貴子、木土博成の計10名で、まずは3名によるレジュメ報告がなされました。
最初にバッツ氏より、「現代社会を理解するため、歴史学者はどのように貢献できるか」という観点から、縦軸より横軸を重視する本書の意義や、勝者の歴史になりがちといった課題が挙げられました。ついで奈良氏は「アジア史と「世界」概念から近世日本と明治維新を考える」と題し、「世界認識」という切り口から本書の到達点を示すともに、ご自身の明治維新史研究との親和性を強調しました。さらに松方氏は、現代人が求めるものを本書は提供していると評価した上で、「戦争」「国家」といった「19世紀言語」を用いている点について、「翻訳」の問題を度外視すべきではないとの見解を出しました。
参加者からは、社会学の成果をふんだんに取り込み、大枠を描いた本書について、「グローバルエリート」の養成というその意図には注意が必要であること、歴史学の立場から中身に当たる事実関係をより丁寧に見ていく必要があること、とりわけその際には地域の歴史が足がかりになること、などの意見が出ました。普段は細かい実証に終始しがちな私としては、大枠を提示する本書に圧倒された思いでしたが、地域史と世界史を繋ぐという観点でいえば、まさに長崎という場でこのような議論ができたことは意義深く感じました。長崎歴史文化博物館の「レファレンスルーム」の目立つところに、『地方史研究』が配架されていることの意味・重みをあらためて考えている次第です。
29日 シンポジウム参加記
シンポジウム「『長崎口』の形成―15~19世紀の長崎から見た日本列島の国家形成と対外関係」は、2019年6月29日(土)に長崎歴史文化博物館で開催された。博物館が会場ということもあり一般の方が多数参加し、ホールの席がほとんど埋まるほどであった。長崎の方々の長崎の歴史に関する関心の高さを窺い知ることができた。
本シンポジウムでは、近世日本において対外関係の窓口となったいわゆる「四つの口」の一つである「長崎口」について、ほかの地域との比較や関連に着目しながら、その形成や意義について再考を行った。プログラム内容は以下の通りである。
松方冬子(東京大学)「『海の道』から『口』へ―長崎を素材に―」
橋本雄(北海道大学)「五島から寧波へ―中世の大洋路―」
織田毅(シーボルト記念館)「長崎の通詞」
村尾進(天理大学)「『広東体制』-『長崎口』との連関・比較」
吉村雅美(日本女子大学)「貿易の記憶と記録―平戸から見た長崎・五島―」
海原亮(住友史料館)「長崎に銅を送る-大坂からみた長崎-」
司会:平岡隆二(京都大学)
松方氏は「四つの口」を巡る議論を整理し、長崎口の形成とその特性について議論したが、「四つの口」が史料上に見られる用語ではないという指摘は、重要であろう。「四つの口」がそもそもどのようなものなのか、「四つの口」論が果たして妥当なのか、実態研究の深化が待たれる。
橋本氏は中世の航路について報告した上で、なぜ長崎が近世に「長崎口」となったのか分からない、という疑問を提示したが、そのような問い自体、筆者には考えたことがないものであった。今まで、立地や幕府直轄領であったことが作用したのであろうと漠然と理解していた。しかし中世は博多、平戸、五島といった東シナ海に面した港が重要な港であり、長崎湾に深く入りこまなければならない長崎が一大貿易港になったのは自明のことではないという指摘は興味深いものであった。平戸などの貿易港がなぜ「口」として選ばれなかったのか、ほかの「口」の形成や動向とどのような関係にあるのかなど、まだまだ検討すべき課題が多く残されていよう。
織田氏の通詞や海原氏の銅の供給・運搬についての報告を通して明らかになった長崎のあり方も、ほかの「口」と比較することで「長崎口」の特質を理解する手がかりとなると思われる。
吉村氏の平戸の貿易の記憶と記録を分析した報告は、長崎に貿易港としての地位を奪われた平戸で、貿易と関連してどのようなアイデンティティが形成されたのかを明らかにしており、それが明治以降の「鎖国」研究や南進論に影響を与えたという指摘は興味深かった。
また、村尾氏の長崎に外国商船の入港・滞在を限定するというあり方が、清の「広東体制」の形成に直接影響していたという指摘は、「長崎口」を世界史的視野で考える際に非常に重要である。「長崎口」の特質と普遍性を考える上で、ほかの「口」だけではなく、世界の国際貿易港との比較の視点も常に忘れずにいる必要があるだろう。「長崎口」の再検討は始まったばかりであり、「四つの口」論の再検討が、日本近世対外関係史の見直しとなるだけではなく世界史として論じられるためには、日本史以外の研究者がどのような問いを投げかけ、参考事例を提示できるかも重要であることを感じた報告であった。

(シンポジウム風景1)

(シンポジウム風景2)
30日 巡検参加記
最終日は長崎学研究所の赤瀬浩さん、藤本健太郎さんのご案内のもと、長崎巡検を行った。前日の予報では警報レベルの大雨が心配されていたものの、当日は傘をほとんど使うことなく巡検を行えたことは幸運だった。巡検では出発時にいただいたカラーの美しい古地図を片手に、①聖ドミンゴ教会②代官所跡③桜町牢屋敷跡(長崎市役所)④深堀騒動跡(大音寺坂、高木彦右衛門屋敷)⑤土佐商会跡⑥思案橋・丸山遊郭跡⑦小島養生所跡⑧唐人屋敷跡(福建会館、土神堂、天后堂)⑨旧居留地⑩旧上海銀行長崎支店跡をまわる盛沢山の内容であった。案内を聞きながら自分の脚で歩いてまわることによって、長崎の街の様子、距離感、歴史的変遷を直接肌で感じられたことは貴重な体験であった。起伏に富む長崎の街に体力的な疲れを感じながらも、そんな疲れを吹き飛ばしてくれるような赤瀬さんのユーモアあふれる軽妙な語り口に引き込まれ、とても充実した巡検であった。
中でも個人的に興味深かったのは、内町を囲む立派な石壁の存在である。戦後の地図にもくっきりと形が確認できる石壁は、部分的な修復を重ねながらも今日まで存続しており、想像以上に立派な佇まいが印象的であった。またイタリア史専門としては、唐人屋敷跡にローマのゲットーとの共通点が多々見いだせる点も興味深かった。ユダヤ人を市内の一角に隔離する目的で1555年にローマに創設されたゲットーは、トレント公会議後のカトリック側の態度の硬化を象徴するものとして、その隔離の側面がこれまで注目されてきたが、近年ではゲットー創設後もローマ人とユダヤ人の間の交流、伝統的つながりが継続されていたことが見直されてきている。唐人屋敷に関しても、敷地の周りを濠が囲んでいる点はゲットーに比べて隔離が徹底されているようにも思えるが、その一方で「キャッチボールができる距離」と赤瀬さんが表現されたように、現実には長崎の人との交流が存在していたことがうかがえた。さらに聖ドミンゴ教会をはじめ、建物の立て直しの際の発掘調査によって多くの遺物が発見され続けている点も印象的であった。すでに建物が建っていたために出ないだろうと言われているところも、掘れば出てくることがよくあるとのこと、今後長崎県庁跡地の発掘調査が行われることによって、新たな遺物が発見されることを期待したい。
今回の巡検を通じて、「口」として外に開かれ、世界とのつながりを有してきた長崎という街の柔軟性、包容力を随所に感じることができた。入ってきたものを受け入れ、そして長崎化させる力こそ、歴史的に育まれたこの街の最大の魅力であろう。また街の歴史を観光資源としてだけではなく、県民のための利用を積極的に進めていらっしゃるお話を東山手十三番館にてうかがえたことも非常に興味深かった。
(貴重な機会を与えていただき、赤瀬さん、藤本さんに心より感謝申し上げます。)

(サン・ドミンゴ教会跡/末次平蔵居宅跡/長崎代官屋敷跡)

(内町と外町を隔てる石垣)

(唐人屋敷 土神堂)

(唐人屋敷外周の空堀)
研究代表者から
以下、主催者の立場から、成果として得られたことを簡単にまとめて見たいと思います。
まず、読書会の私なりの結論は、「自分にとって身近な地域とつながっていない世界史は興味を持ってもらえないらしい」ということです。「世界」が、自分を含まない、どこか遠くにあるものだと思われては(思っては)ならない、あるいは、ごく一部の人たちだけが占有するものであってはならない、ということでしょうか。世界が自分とつながってくれるのを待つのではなくて、自分が世界とつながっていく、そのために何が必要か、というのが、翌日の課題となりました。
29日のシンポジウムは「四つの口」論が崩壊した(!?)とは言わないまでも、根底からの再考を迫られた、日本近世史にとって画期的な瞬間だったような気がします。
私は勝手に、「口」を「独占主体」としてイメージしていましたが、日本語としては「出口」「入り口」の「口」、英語で言えば、Entrance, Window(バッツさんご教示)、だと指摘されました。「壁にあいた隙間」のイメージが強いということになりましょう。しかも、日本語の用法として、たとえば「丹波口」は「(京都から)丹波に行く(向かう)口」であって京都にある。丹波のこと(丹波にあるわけ)ではない(木土さんのご指摘)。「四つの口」は「最近では小学校教科書にも載っており人口には膾炙しているが、史料的根拠はないみたいだし、あまり良くないのではないか?」という意見がいくつも出されました。では「四つの」何と言えばよいのでしょうか?
また、「四つの口」がどこに落ち着いたかについては、権力の意向も大事だが、何と言っても立地や環境、地政学的要素が大きいと改めて認識できました。
ちなみに、シンポジウムのレジュメ配布数は、132でした。一般向きの講演ではなく、学術の最先端でも、これだけの人たちが来てくださることに感動しました。世界史を扱おうとすると、それぞれの専門がばらけますので、全員が「素人」になれて、話がわかりやすくなるのは良いことかもしれません。
巡見は、多くの参加者から「観光地でない長崎を見られた」「何度も来ているが、こういう景色は初めて」などの感想が寄せられました。また、社会実験(NPOによる大浦居留地の洋館活用。おもに高齢者のパワーを借りて、カフェを運営。)の現場などもご紹介いただき、学ぶところが多々ありました。
(本ページの無断転載を禁止します。)