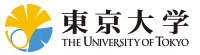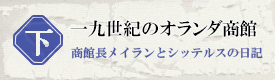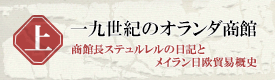東京大学ヒューマニティーズセンター公募研究
LIXIL Ushioda East Asian Humanities Initiative
2018年10月~2019年12月
徳川政権の外交 ―あるいは「外交」以前―
Tokugawa Diplomacy: Diplomacy Before Diplomacy
2019年12月20日オープンセミナー特別回
(コーディネーターとしてセミナーを終えて)
オープンセミナー特別回「社会科学と人文学の対話」は、和やかな中にも活発な討論が行われ、大成功だった。
当初、社会科学は未来を構想し、人文学は現在を振り返る(筋肉で言えば、社会科学が「鍛える」、人文学は「ほぐす」)という違いがあると思っていたが、セミナーの議論を経て、山下範久編『教養としての世界史の学び方』(東洋経済新報社、2019年)、松方冬子編『国書がむすぶ外交』(東京大学出版会、2019年)の違いは、むしろ想定される読者の違いであるように感じられた。
どちらも西洋中心主義から世界史を解放するべく、時系列史に疑問を呈しつつ、空間把握・「19世紀言語」という切り口で世界史を考え直そうとしている点に共通点がある。同じ場所から出発して、『世界史の学び方』が(新しいコンセプトを武器に?)徹底して空間把握や「19世紀言語」を問い直す方向へ向かうのに対し、『国書がむすぶ外交』は実証的な文献史学の手法を武器に不十分であっても対案を提示しようとする。
フロアから「『19世紀言語』を批判することで、研究が一般社会から離れてしまうのではないか」という質問がなされ、それに対する山下氏と松方の答えは同じく「19世紀言語のほうが一般社会から遊離しつつある(あるいは一般社会が19世紀言語に収まらなくなりつつある)と思う。」「そもそも、日本人の生き方考え方が『19世紀言語』に収まっているとは思えない。」というものであった。その現状に鑑み、『教養としての世界史の学び方』『国書がむすぶ外交』がともに提起しているのは、「21世紀の日本列島に生きる自分自身の感性から出発しよう」「納得できないことは納得できないと言おう」ということではないかと思う。
『教養としての』というタイトルは、おそらく『大人のための』の言い換えである。「子供のための世界史の学び方」は、善し悪しはともかく、「ともかく教科書を丸暗記せよ。感じた疑問は受験の邪魔になるから、フタをして忘れろ。」となってしまっている(それが大人社会から子供たちが受け取るメッセージであろう)。逆に言えば、とくに自分の疑問とか、動機とか、そういうものがなくても、強制されて学ばされる(学べる)のである。しかし、大人になったら、そうはいかない。自分で学びたいと思わなければ、学ぶことができない。強制力のないところで、自分のなかに「学びたい」という動力を見出すにはどうしたらよいか。『教養のための日本史』なら、博物館や自宅の物置で見つけた掛け軸とか、そういうものをヒントにすることはできるだろうが、世界史を学ぶにはもう少し別のヒント(出発点)が必要である。
我々は、ダテや酔狂で21世紀を生きているのではない。21世紀の日本列島に生きるということは、外国に行ったことがなくても、英語が苦手でも、否応なく世界の中で生きるということである。自分自身を大事にしよう。もし、今まで学んできたことに、モヤモヤを感じるなら、そのモヤモヤのなかに、かけがえのない自分がいる。(もちろん、モヤモヤにフタをして生きるすべを身につけた自分も悪くないのだが、そちらはほかの人と同じ、言い換えれば稀少性のない自分である。)モヤモヤに取り組んでみれば、世界にたった一つしかないオリジナルな考え方をひねり出すことができるかもしれない。『教養としての世界史の学び方』が世に伝えたいことは、つまり、「自分を足場にせよ」というメッセージではなかったか。ここで、対案を出す必要はない。対案を出したら、読者は自分のモヤモヤでなく、編者・執筆者の対案のほうを(最悪の場合)丸暗記してしまうかもしれない。サラリーマン諸氏は、そんなにヒマではないから、プロの対案に対して批判を組み上げる時間はないだろう。
それに対し、『国書がむすぶ外交』は、プロ向きの学術書である。こちらには対案が必要である。仮説を示さないと、批判や反論が返ってこない。実際に、タイや韓国の研究者から「日本に偏った見方だ」という批判が来ている。そういう批判は大歓迎である。批判を受け取るために書いたのだから。すべての学説は仮説である。こういう場合、実証史学の批判はたいてい「あなたの仮説には、こういう反証(当てはまらない事例)がある」という形で来る。そうやって寄せられた事例を集めて、また新しい仮説を作ればよい(私がやらなくても、誰かがやるだろう)。
私は「実証は嘘をつかない」と思う。実証史家は論を立てるのが苦手なので、(私を含め)自分の実証とうまく合わない総論を書く人が良くいる。実証と総論がズレている本や論文があったなら、私は実証のほうに、著者の本当の想いが入っていると思う。なぜなら、実証には時間と手間暇がかかる。その時間と手間暇をかけるだけの動機が著者のなかにある。総論のほうは、世の理解を得るために、学んだ枠組みに無理やり当てはめて書く場合もあって、そういうときは、とってつけたようなことになる。
では、どうすれば、実証から、論を立てることができるのか。私の暫定案は、なるべく幅広い研究者によるなるべく幅広い実証を集めることである。3人の研究者がいて、20世紀のイギリスと、19世紀のロシアと、17世紀の日本を研究している。もし、その3人の研究に響きあうものがあるなら、それは、研究対象ではなく、21世紀に生きる研究者同士が響きあっているのである。もし、その3人が全員女性なら「女性だから」響きあっているかもしれないし、全員日本人なら「日本人だから」響きあっているのかもしれない。でも、もし、性別や国籍や年齢がバラバラなら、「21世紀の世界」がそこにみえてくるだろう。
響きあっても、言語化することは難しいし、苦しい。わかったふりをして、通り過ぎるほうが、格好良く見えるかもしれない。けれども、「どんなに格好が悪くても、自分自身から出発するしかない」というのが、恩師吉田伸之氏(日本近世史)から、いただいた言葉である。結局、分野とかそういうことはあまり関係なくて、研究とは、そういうものではないだろうか。
2019年11月29日オープンセミナー特別回
・「王の手紙、皇帝の文書:─外交の世界史に向けた韓国、タイ、日本の鼎話の試み」
・Royal Letters, Imperial Documents: A Japanese, Korean and Thai Trialogue for a Global History of Inter-State Relations


2018年10月26日オープンセミナー
2019年7月12日オープンセミナー
(本ページの無断転載を禁止します。)